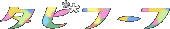旅先での燃ゆる思いを綴ってみました。
ご感想・ご批評等はメールか掲示板で。
ご注文は?
米のメシが一般的な、南インドでのお話。
ある朝(といっても一般的に言うところの昼つまり私達にとっての朝)、
お腹が減ったので町のレストランに入った。
どうやら私達が朝一番(といっても昼)の客だったらしく、
店長らしき恰幅のいい男性と口髭のチャーミングな店員が、ことさら丁寧に出迎えてくれた。
メニューをテーブルに置き、にこやかに「ご注文は?」と訊ねるので、
「そうね、じゃあブリヤニ(インド版のピラフみたいなもの)を頂戴。」と言うと、
口髭の店員は大げさなほど驚いた顔をしながら、
「ええっ?ブリヤニってあなた、当店はつい先刻開店したばかりですよ?」と答える。
しばらくは意味が分からなかったが、つまりブリヤニは用意できないということらしい。
よく考えれば、ブリヤニは意外に手の込んだ料理のようにも思えるので、
朝っぱら(といっても昼)から注文するのはインド的に非常識なのかなー、なんて思い直し、
「そう、ではターリー(インドの国民的定食)でいいわ。ライスもね。」と言うと、
今度はもう呆れたと言わんばかりに鼻で笑いながら、
「ですから、当店は開店したばかりなので、ライスはまだありません。」と言う。
私はその朝(といってもその日に限ったことじゃなく日常的に)、
米のメシを食べないとお腹が膨れた気がしないモードだったから、
しばらくメニューとにらめっこした挙句、その店を出ようと旦那に促した。
旦那はその朝(といってもその日に限ったことじゃなく日常的に)、
起きてしばらくは食欲ないんだよねモードだったので、
「まあいいじゃない、チャイだけでも飲んで行こうよ。」と私を諭した。
それでチャイをふたつ注文したが、案の定「ノーチャーイ、マダーム」と口髭。
例えるならそれは、茶そばもそばも茶もないのに営業中のそば屋。
インドには、最初の客を逃すと一日の商売がうまくいかないというジンクスがあるのだが、
きっとその日、そのレストランは大赤字だったはずだし、これからも毎日そうだろう。
ワタル売り
日本人は英語が苦手で、その発音の特異性は「ジャパニングリッシュ」と表されるが、
インドにもまた、「ヒンディングリッシュ」が存在する。
英国人をもってしても難解だという「ヒンディングリッシュ」の最も顕著な特徴は、
R(アール)を巻き舌で発音することである。
カルカッタからチェンナイに向かう列車内には、
北インド出身の客と南インド出身の客が混在するため、
物売りの多くが、準公用語である英語を使って飲み物やおやつを販売していた。
(インドでは、地域によって使用される言語が異なるので、
共通語とされるヒンドゥー語、もしく英語を使えないと、
たとえインド人同士でも、会話が成り立たないのであります。)
築地の魚河岸を彷彿とさせる、しわがれたダミ声のサモサ売りや、
自分の身体と同じくらい大きな給湯器を抱えた、チャイ売りの少年。
その中に、ワタル売りがいた。「ワタル〜!ワタルはいらんかね〜!」
さて、ワタル売りが扱っていた商品はなんでしょう?
北インドを旅してる間、特に観光地化されていない町の一般庶民に対しては、
「本当に準公用語なの?」って疑いたくなるくらい通じなかった英語だが、
イギリス統治の影響をもろに受けていた南インドでは、
全体的な教育水準が高いことも手伝い、その通用度が極めて高い。
ていうか、みんなふつーに英語で会話しているから驚いた。
問題はその英語が「ヒンディングリッシュ」だということだ。
発音だけならまだしも、皆さんネイティブスピーカーのスピードで話すもんだから、
ぽっと出の旅行者である私達には、ちょっとやそっとじゃ理解できない。
昨日なんか、もう何十回も場数を踏んで手馴れてるはずの安宿のチェックイン時に、
フロントの親父に「ユラパスポルトナンバル プリーズ!」と言われ、
5秒くらいの間、頭の中が真っ白になった。
さて、フロントの親父が求めていたユラパスポルトナンバルとはなんでしょう?
そうそう、興味深いことに、北インド(の観光地)で出会った英語使いの多くは、
南インドのエリート達より、格段に聞き取りやすい「ヒングリッシュ」を話した。
それは、彼らの英語が教科書で教わった屁理屈なんかじゃなく、
旅行者と接しながら肌で覚えた、商魂たくましさの賜物だからに他ならない。
(その証拠に、会話は出来ても“読めないし書けない”輩が多いのだった。)
やるなー、北のインド人。
そんなこんなで、ワタル売りが売っていたのは「水(WATER)」、
ユラパスポルトナンバルは「あなたの旅券番号(YOUR PASSPORT NUMBER)」でした。
トイレがない国
インドとネパールの国境の町で、ひとり旅のドイツ人と袂をかすめた。
彼女はこれからネパールへ、私達はいよいよインドへの入国を控えたところで、
その、おそらくもう二度と会うことはない旅人と、
私達はチャイを飲み交わし、それぞれの旅の話を披露して、ひとときを過ごした。
話題が中国に及んだ時、彼女が不意に「トイレの話を聞かせてよ」と言う。
私が、大げさに目を見開いて「我慢できる?」と聞くと、
彼女はククッと笑って「聞きたい」と答えた。
ネパールから帰国を予定している彼女が、中国の、しかも便所だけに興味を持つ姿は、
これまでに他の旅人から聞かされてきた、想像するだけで気の遠くなるような不浄が、
本当にこの世に存在するのか、確かめているかのように見えた。
私は面白くなって、ボディランゲージや図解も取り入れながら、
できるだけリアルに中国のトイレを再現して見せ、
彼女は、声をあげて笑い、ひとしきり腹を抱え、最後にこう言った。
「中国のトイレがどれだけ汚いかってこと、よくわかったわ。
お返しにひとつ教えたげる。
あなたがこれから行くインドって所はね、
汚いんじゃなくて、ないのよ。トイレがない国なの。
我慢できる?」
かくしてインドには、トイレがなかった。本当になかった。
もちろん、ホテルや列車や駅や高級な場所にはあるのだけれど、
ネットカフェで急にもよおして「トイレどこ?」と聞いても「ない」。
レストランで急にもよおして「トイレは?」と聞いても「ない」。
そりゃ、トイレを設けてない食堂やネットカフェは、他の国にだってあるけど、
そこで働く人がいる以上、彼らが普段使っているトイレが、
店内じゃないにしてもどこか近くにあるはずで、
普通だったら「トイレどこ?」の問いに、その秘密のありかを教えてくれるってもんだ。
ところが、インド人の答えはいつも決まって「ない」。
「ここにはないからあの店でお借りなさい」とか「道の向こうの公衆便所があるよ」ではなく、
「ない」なのだ。「ないったらない」のだ。
それで旦那が、「じゃあ、あんたはどこでしてんだよ?」と聞くと、
揃いも揃って皆「(小)か?(小)ならその辺でして来いよ」と、外を指差す。
それで私が、「じゃあ、(大)ならどこにしてるのよ?」と聞くと、
揃いも揃って皆「はて?どこでしてたっけ?」というトボケタ顔をする。
とにかく、旦那は(大)、私には(大)(小)とも排便する場所がない。
仕方なく、あわてて宿の自室に駆け戻る。
インドを旅する旅行者にとっては下痢なんか日常だから、
下腹部にそんな気配を感じたら、容赦なく尻を押さえて駆け戻る。
インド人は脱糞排尿しないのかって、もちろんそんなことあるわけない。
インド人だって人間なのだ(そりゃかなり人間離れしたのも多いけど)、出るもんは出る。
なのに出るもんを出す場所がない。だからどこにでもする。その辺にする。
どこでもトイレ〜。ドラえもんの道具ならシャレになるけど、それが国土全体だと困る。
それでも、インド人にも小指の爪の先ほどは羞恥心ってものがあるようで、
一応は人通りの少ない路地や、道端の草むら、木陰でしゃがみ込むのだが、
部屋のベランダやリキシャーの上から、少しでも見下ろそうものなら、
目の中に見たくもないウンチング姿が飛び込んでくるのは、テロよりも避けられない。
ある時、列車の中で目を覚まし、朝焼けでも見ようかと窓の日除け幕を上げたら、
線路沿いの用水路に、インド人がしゃがんでいるのが見えた。
20m先にも、その20m先にも、またその20m先にも
計ったかのような等間隔をおいて、何人ものインド人が並んでいた。
用水路の奥の雑草地にも、時折インド人の頭が見えた。やはりしゃがみ込んでいた。
小魚でも釣っているのかと、寝ぼけた頭でぼんやりとそれを見ていた。
通勤の時、車窓に流れる電柱を目で追ったのと同じように、ぼんやり見ていた。
しばらくして、それが小魚を釣っているのではなく、餌をやっている風景だと気付いた。
尻からにょろり、栄養価の高い芳香な餌を。
その朝、私は実に50例もの脱糞風景を見た。
朝焼けどころか胸焼けも甚だしい一日の始まりだった。
そしてそれが、まさにインドがインドでありインドらしくあるための、毎朝のセレモニーなのだ。
旅を続けているうちに、いかにもインドな話を耳にした。
千葉なのに東京だと言い張っている巨大テーマパークで、
六年間働いていたという女性から聞いた話だ。
そのテーマパークの呼び物のひとつに、
敷地の中心に位置する、ディズニーのシンボル的存在なお城の内部を、
歩いて周るアトラクションがある。
そのミステリーツアーに参加していたインド人観光客が、
城の暗がりでウンチングしちゃったというのだ。
運悪く居合わせたミッキーマウスが、そのブツを踏みつけちゃったか否かは知らないが、
とにかくその後、インド人の落し物は迅速かつ秘密裏に処理され、
異臭が収まるまで、シンデレラ城は完全に閉鎖された。
夢の国の夢の城はインドと違うわけだからその辺にウンコなどあってはならないし、
夢の国の夢の城で秘密裏にウンコが処理されることなどあってはならないので、
この事件は、関係したキャスト全員に固く口止めされ、
絶対に外部に漏れぬよう、封印された。
「もう何年も昔の話だから、時効ですよね」
元キャストの女性は言った。
彼女はもうすぐ、初めてのインドに渡航する予定でいる。
国際愛煙家同盟
世界中の先進国で嫌煙運動が進む中、
愛煙家の立場は日に日に厳しくなってゆくばかりだが、
少なくともアジアの、私達がこれまで訪ねた発展途上の国々の中では、
タバコを吸うのに法律や周囲の目を気にしなければならない国は、ひとつもなかった。
むしろ、「こんなところで吸っていいの!?」という場所にまで平然と置かれた灰皿や、
吸いカスの捨て場などおかまいなくここそこでモクモクやる現地の人々を、見てきた。
喫煙歴十五年をほこる私には、これは本当にありがたいことで、
現地のタバコを何種類か試しては、その中のお気に入りを、
目覚めて一服、クソして一服、朝から晩までスモーキン・ブギしている。
そんな風景をいつも不愉快そうなに見ているのが、ヨーロピアンの嫌煙家達だ。
もちろん、タバコを愛する白人さんだってインドの牛の数ほどいるし、
日本にも他のアジアの国々にも、タバコの煙を苦々しく思う人は大勢いるんだろうけど、
特に欧米では、公共の場所での喫煙になんらかの規制が置かれているせいなのか、
彼らの煙に対する忍耐力は、アジアの人々のそれに比べてかなり低いように感じる。
そして、一部の欧米人が持つ黄色人種に対する差別的な思想がそこに加われば、
なおのこと、その表情は険しくなる。
チベットで出会った羽織ハカマ姿のバックパッカー、グレネコさんは、
ある日こんなシーンに出くわしたそうだ。
アジアのとある国のインターネットカフェで、
当然のように置かれた灰皿を面前にプカプカとやっていたところ、
数人のヨーロピアンが、手で煙を振り払うようなリアクションをした。
謙虚で律儀で情の深い国民性を持つ、我が同胞のグレネコさんは、
それを見て、すぐにタバコの火を灰皿に押し消した。
ところが連中は、そんな謙虚で律儀で情の深い行為を目前にしてまで、
さらにこう言い放ったのだそうだ。
「Disgusting Japanese!!(いまいましい日本人野郎め!!)」
謙虚で律儀で情は深いが、他の多くの同胞とは違い英会話に長けるグレネコさんは、
その時、自らに流れる日本男児の血がフツフツと沸きあがるのを感じた。
そして次の瞬間、手に灰皿を持ってこう返したのだそうだ。
「あれれ、これは何かニャ?ここってタバコOKだよニャー?」
「ここはイエローモンキーの国ニャ、こっちのルールに従えニャー!」
「いい考えがあるニャ、お前ら自分の国に帰れニャ!」
こんな話を聞いていたからか、
このところ一部の西洋人が見せる差別的な態度に腹を立てていたせいか、
私は、嫌煙ヨーロピアン達の、タバコに対する嫌悪的な表情や言動に、
きっとすごく敏感になっていたのだと思う。
ブッダガヤーのネットカフェで、ひたすら回線の遅いネットをそれでも楽しんでいた時、
その小さな店内にデカい図体を押し込もうとしていた欧米人の男が、
ちょうどタバコの先に火を点けた私を見て、あからさまに不愉快そうな顔をし、
ガラスの引き戸を開いてウェルカムしているインド人店員に向って、
「タバコ吸ってる奴がいるから他のカフェを探す!」と言ったことに、
一瞬で、キレてしまった。
よくよく考えてみれば、いくらアジアだからって、いくら禁煙じゃないからって、
そんな狭い空間で無遠慮にプカプカやっていた私の方が悪かった。
愛煙家の権利が過剰なほど認められている国々を旅してきて、
感覚が麻痺していたのかもしれない。
まして彼は、自分に見合う‘禁煙ルール’の店を探すと言ったのだし、
私個人や愛煙家や他のアジア人を屈辱するような言葉を吐いたわけでもない。
けれどその時は、自分の主張をするためなら他の人間の、
つまりこの場合、一服しながらネットを楽しんでいた謙虚で律儀なこの私の、
ハッピーな気持ちを一瞬で踏みにじるようなことを平気で口に出す神経が、
なんか許せなかった。
それで、まさにグレネコさんがやったのを真似るかのように、
「吸っちゃいけなかった?灰皿あるけど!?」と言いながら、
点けたばかりのタバコを、かなり乱暴に灰皿に押し付けた。
努めて冷静を装ったつもりが、声は上ずり、頬が一気に紅潮していった。
肌を切るような冷たい外気と一緒に、
いかんともしがたい気まずい空気が、店内に流れ込んだ。
嫌煙家の彼は、かなり驚いた表情で扉の外に突っ立っていたが、
私とインド人店員の顔を何度か交互に見比べたあと、
両手を胸の前でパーにし、‘まあまあ落ち着いて’ってな動きをしながら、
「いいんだ、吸い続けてくれよ。」と言って、そそくさと去って行った。
暗がりに消えていく彼を目で追い、もの惜しげな表情でガラス戸を閉めた店員は、
しばらくすると踵を返し、すっかり赤ら顔の私に、
「吸ってていいんだ、ここは禁煙じゃないからノープロブレムさ。」
と、その困り顔を無理に笑顔に変えながら、まるでなぐさめのような声をかけた。
天才的に楽天的な旦那も、「いいんじゃない、気にしなくて。」と、こともなげに言った。
感情っていうガソリンで爆走した後って、いつだって苦々しい後味が残るもんだ。
不快感と恥ずかしさも手伝って、私はまだかなり動揺していた。
開いていたサイトの文字なんか全然目に入ってこなかったし、
せっかくのお客を逃してしまったようで、店に対しても申し訳ない気持ちだった。
小さな店内でネットをしている他の数人の客は、不運なことにほとんどが欧米人で、
その全員が私を責めているように思えて、私は何度か、こそこそと店内を見回した。
国際愛煙家同盟の狼煙(のろし)があがったのは、その時だった。
気弱な視線に気付いたひとりの白人男性が、私に向って小さくウィンクした後、
ポケットからタバコを取り出し、おもむろに火を点けたのだ。
すると、それを見ていた隣の女の子も、またその隣にいた男性も、
それまでタバコなんか吸っていなかった他の客達が、
ほとんどみんな一斉に、それぞれのタバコを口に咥えた。
見る見るうちに店内は、目がショボショボするほどの紫煙で埋め尽くされ、
数少ない灰皿は、多国籍な愛煙家達の手に手を伝って、店内を何周も巡らされた。
もしかしたらそれは、私へのエールであると同時に、
いつも自分の国で嫌煙運動に虐げられてるうっぷんを、アジアの片隅で晴らしたという、
ささやかな勝利の一服であったかもしれない。
このところ様々な理由から敵対心をフツフツとさせていた、白い肌を持って生まれた人達に、
私は再び親近感を覚え、照れ笑いを堪えるほっぺたがむずむずした。
そして彼らの粋な行動が、煙が目にしみるのと同じくらい、胸にしみた。
背後であげられた愛煙家同盟の狼煙に気付いているのかいないのか、
日本を出発する少し前にタバコから卒業したばかり旦那は、
黙々とネットサーフィンを楽しんでいた。
これ見よがしに煙を吐く私の傍らで、堂々と禁煙に成功した男だ。
これくらいの煙には、ビクともしないのである。
絶世の名馬
バラナシから、何時間も遅れたのに申し訳のひとつもない列車に乗り込み、
悪夢のような混雑の二等自由席でもみもみくちゃくちゃにされ、
ほうほうのていでガヤーの駅に到着したのは、すでに草木も寝仕度を始める時刻だった。
それで、そこからさらにリキシャで数十分を要する目的地・ブッダガヤーへの移動を諦め、
私達は、駅前のロータリーにある薄汚い食堂の二階に、一晩の宿をとった。
翌朝、宿をチェックアウトした私達は、ブッダガヤーに向かうための「馬」を探して、
大きな荷物を背負ったまま駅前をうろうろしていた。
なんで馬かと言うと、ただ単にそこに馬がいたからだ。
馬の後ろに牽かれた荷台に粗末な座席を施した、「タンガ」と呼ばれる馬力タクシー。
インドの、ちょっとした田舎では、割と一般的な乗り物だが、
なんせ遅いし、揺れるし、馬がうんこ垂れながら走るもんだから臭いしで、
そうそう滅多には乗る機会もない。
でもま、ガヤーに一泊したおかげで、今日は時間に余裕がある。
移動にいささか時間をかけても、昼時にはブッダガヤーに到着できそうだ。
たまには馬の歩みのペースに任せて進むのも悪くない。
獲物に群がるハイエナのようなリキシャの客引きをかわしながら、何匹かの馬に声を掛ける。
「ヒヒヒーン、ヒヒン、ヒン?」
「ヒヒーン、ヒンヒン!」
馬達は、喜んで乗せてやるよと奮起してくれている。
ところが、荷台でその手綱を引くインド人どもが、
「ブッダガヤーまで?300ルピー(=約750円)でどうだ。」とか寝惚けたことを言うのだ。
ガヤーからブッダガヤーまで、距離にして約15キロ。
駅からはかなり離れた場所にあるガヤーのバス停までなんとかしてたどり着けば、
そこからほんの数ルピーで、ブッダガヤー行きの乗り合いバスに乗れるというのに。
「ブッダガヤーまで150ルピーでどうだ?」「いや俺なら100ルピーで行ってやるぞ。」
耳元では、オートリキシャの客引きさえもそう言っている。
馬にならまだしも、おんどれに300ルピーなんて払うものかと、憤然と値下げに挑む私。
ところが、いくら交渉しても、馬使いは100ルピーから値段を下げない。
100ルピーといえば、タンガ御者の一日分の収入に相当する額だ。高過ぎる。
馬使いを挑発するために、すぐ隣でオートリキシャと値段交渉する旦那から、
「おい、こいつ50ルピーで行くって言ってるよ。」と声がかかった。
50ルピーなら、ガイドブックで紹介される相場をも下回る価格だ。こりゃおいしい。
それで、あえなく馬での出陣を放棄、リキシャでブッダガヤー入りすることに決定した。
最安値で私達を落札した運ちゃんは、インド人にしてはかなり恰幅が良く、髭もたわわで、
どこかリキシャーワーラーらしからぬ威厳を漂わせた男だった。
顔をむっつりとさせ、愛想笑いのかけらもなく、あごをプイと上げて「乗れよ」と指示する。
日本ならこんな時「嫌な運転手に当たっちゃったな〜」てなもんだが、インドでは逆だ。
こういう不器用そうな男こそが、かえって信頼できる。
あざといインド人ほど愛想が良く、語学にも堪能なのだから。
ただ実は、この男の体型だけが、私達の心配の種ではあったのだが。
(肉付きがいい→いいもん食ってる→儲かっている→旅行者をカモにした悪党?)
私達の小さな不安を知る由もなく、運ちゃんは黙々とオートリキシャを走らせる。
無駄口も、ツアーや土産物の売り込みも一切無しだ。
ただ一度、ガヤーの街外れの小さな商店で唐突にリキシャを止め、
顔見知りらしき人相の悪い男に、もごもごと話しかけた。
人相の悪い男が私達をチラっと見て、ニヤリと不敵な笑みを浮かべたので、
どこかに連れ込まれるのではと一瞬背筋を冷やしたが、
男は、自分の商店からなにやらを持ち出して運転手に手渡すと、また店へ戻っていった。
髭の運転手はというと、その間にふらりとリキシャから降り、
そこらの草地で一瞬しゃがみこんだかと思いきや、またすぐに運転席へと戻った。
インドでは、男性でも座りションするのが普通なので、
ずいぶんとおしっこのキレがいいんだなと思って見ていると、
運ちゃんはおもむろに振り向き、
草地で拾ってきたらしい細い木の枝を、なぜか私の右手にむんずと握らせた。
それが何を意味するのか考えるよりまず、
おしっこが付着しているんじゃないかと、厳重に小枝をチェックする私達をよそに、
今度は、人相の悪い商店主から受け取ったなにやらをもぞもぞとまさぐる髭。
取り出したブツは、私達にはなんとも物騒なものに見えた。ロープだったのだ!
はっと顔を見合わせる夫婦。無意識に、手にしたばかりの小枝で身構える。
だがそれが、二人の大人を拘束するにはあまりに細いロープだとすぐに気付いた。
髭は、私達が無駄に動揺していたほんの一瞬のすきに、
手早くロープを運転席の後部にくくりつけ、
その大きな輪の一端を、またしても私の左手にくるりと絡めて掴ませた。
そして、例によって笑顔のひとつもないまま「これを離すなよ」と念を押し、
呆気にとられてポカンと口を開ける私達に背を向け、リキシャを発進させた。
インドの北部は、バラナシなどの主要な地区を以ってしてもインフラの整備が悪く、
地方に行けば、道のデコボコなんて当然のことだ。
それにしたって、ブッダガヤーへの道はそれほどの悪路なのだろうか?
万が一にもリキシャから振り落とされては大変と、旦那にもロープを勧めてみるものの、
「なんでそんなん持ってる必要があるの?揺れもしないじゃない。」と言われ、実に納得。
右手の小枝に関しては、頭上にハテナマークを浮かべるしかない。
夫婦と荷物とロープと枝と多くの謎を乗せたまま、そのまま二十分も走っただろうか。
周辺にはまだ、畑とも野原ともつかない緑の絨毯が敷き詰められているが、
その中に、深いエンジ色の袈裟を着たチベットの巡礼僧を、ちらほらと見かけるようになった。
ブッダガヤーは目前だろう。
ふと見ると、前方で、タンガが馬に牽かれてゴットンゴットンと音を立てている。
やはり緑の風景によく合う、情感漂わせた乗り物に違いない。
あれに乗るはずだったのに。追い越しざま、物惜しい気持ちで馬の横面に目をやった。
その瞬間。
「んあああああああああああああ!!!!」
私は思わず、馬も驚くほどの大声を上げていた。
頭の上でふわふわしていたハテナマークが、瞬時にビックリマークに変わる。
「なんだよおい!忘れ物か?パスポート忘れたか?」と慌てる旦那を制止し、
私はさらに、「はいやァ!はいやァァァァァァ!!!」とあらん限りの声を張り上げる。
同時に、右手の枝で運転席の背をぴしぴしと叩き、左手のロープを何度も振り下ろした。
「むああああああああああああああああ!!!!」
今度は旦那が絶叫する番だった。
二人で顔を見合わせ、それこそリキシャから転がり落ちんばかりに大笑い。
ミラー越しに髭の運転手と目が合うと、奴は初めて、ニンマリと黄ばんだ歯を見せた。
ガヤーの駅前で、私達が何匹もの馬、いや馬使いと交渉している姿を見ていた髭は、
自らを馬に見立て、自ら手綱と鞭を用意し、私達にタンガ気分を味あわせてくれたのだ。
ちょっとした冗談のつもりだったのだろうが、危うく気付かずに降り去るところだった。
微かに満足気な表情でアクセルを握る髭。
「はいやァ!はいやァ!」
鞭を増やすと、心なしかリキシャのスピードが上がったような気がした。
私達を乗せた即席のタンガは、その後間もなくブッダガヤーの町へ到着した。
髭をたっぷりたくわえた二本足の馬は、私達から約束の50ルピーを受け取ると、
「ヒヒン」とはさすがに鳴かなかったが、小さく「サンキュ」と言って走り去った。
最後まで無愛想な馬、しかしながら絶世の名馬だった。
「あんなに素敵なタンガだったら、300ルピー払っても良かったかもねー」と、
まだ手に握り締めていた木の枝であちらこちらをぴしぴし叩きながら、私が言うと、
「甘いな、そんなことしたらインド人につけこまれるだけだよ。」と憎まれ口を叩きながら、
旦那もやはりまだ、ニタニタと笑っていた。
ポエム バラナシで見たもの
バラナシで見たもの。
野良牛、野良犬、野良ヤギ、野良ネズミ。
鳥の死骸、犬の死骸、牛の死骸、人間の死骸。
バラナシで見たもの。
腕のないインド人、皮膚病のインド人、手の指が六本あるインド人、死を待つインド人。
しつこいインド人、放尿するインド人、嘘つきインド人、脱糞するインド人。
それら全てを呑み込んで、ゆるりと流れるガンジス河。
汚れ物を喰らう分だけ、なおも神聖に近づく河。
ガンガーフィッシュp
ガンジスは、ヒンドゥー教の聖なる河であると同時に、
身近で便利な廃棄物処理場でもある。
生活廃水、インド人がその辺に垂れ流した糞尿、野良牛や野良犬の糞尿、
火葬後の遺灰、人間も含めたありとあらゆる生物の生死骸、生ゴミ、生じゃないゴミ。
陸にあって忌み嫌われる物は、すべてガンジスに流すというわけだ。
この河に放り込まれては、コレラ菌すら数時間と生きていられないという。
インド人はそれを「聖なる殺菌パワー」だと解釈しているらしいが、
「コレラも殺られちゃうくらいの強力なバイ菌が生息してる説」が、
旅人の間では、最も有力視されている。
態の良い廃棄物処理場のおかげか否か、バラナシの街では、
外国人旅行者の行方不明事件が後を絶たない。
襲って金奪って(オンナノコならついでに犯して)口封じに殺して、
最後は河へ捨てちゃえばいいんだから、殺人だってお茶の子サイサイだ。
(インド人でも、貧乏だったり妊娠中だったり子供だったりすると、
火葬せずに、生遺体のままガンジスに流される。
上流から死体が流れてきたところで、誰も気にもしないのだ。)
私達が滞在していたさなかにも、ガートで殺害されたヨーロピアンがいたらしい。
大金を両替したところを邪悪なインド人に見られ、後をつけられたのだそうだ。
ついでに、対岸まで泳いで渡ろうとするアホな旅行者も、よく溺れ死ぬ。
もちろん、遺体はまず挙がらない。
ある日、泊まっていた宿のパパに「今日の夕食、うちで食べる?」と聞かれ、
ありがたくご相伴に与ることにした(といっても有料なんだけど)。
ママご自慢のお手製カレー、本日の具は「魚」。
食べながら冗談で「この魚、まさかガンガーフィッシュじゃないよね?」と聞いたら、
パパは、さも当然といった表情で「そうだけど、なんで?」と答えた。
うーん、あんまり笑えないよパパ。
もう半分食っちゃったっつの。
当のガンガーフィッシュは、肉厚で、相当な食べ応えであった。
不気味な生臭さをマサラでうまく隠している。
何も考えずに食べれば、なかなかの美味と言えるだろう。
そういえばこのところ、ずっと内陸を旅しているから、
こんなにフレッシュでジュースウィーな魚料理にありつくの、久々なんだよねー。
とか自分に言い聞かせながら、なんとか前向きな気持ちで食事を楽しんでたら、
旦那が、口に出してはいけない例のアノことを、ボソッと言い放った。
「この魚、きっと人間の死体とか食ってたんだろうなー。」
一瞬にして空気が凍りついた。
翌日のこと。
ガンガー沿いに建つラームナガル城を観光した帰り道、
まさに人間の生遺体が、浮き橋に引っかかっているのを見た。
腕がもぎ取れそうなほど腐敗した遺体のその真上で、硬直したまま動けないタビフーフ。
か、勘弁してよ。
ガンガーフィッシュ、食っちゃったっつの。